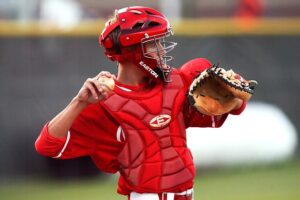2021.08.10
変わるか、終わるか
東京オリンピックが終わりましたね。いくつもの感動シーンがありました。私にとっては空手の形。外国の選手も含め、試合前、試合後の選手の振る舞いが素敵でした。あなたにとって思い出に残るシーンは何ですか? 東京オリンピックは終わりましたが、2週間後に東京パラリンピックが始まります。伴走者が登場する陸上競技に注目です。 突然ですが、テニスプレイヤーのロジャー・フェデラー選手を知っていますか?ツアー通算111勝、グランドスラム20勝というとんでもない選手です。2018年には36歳で世界最年長の世界ランキング1位も達成しています。 錦織圭選手が登場するはるか前の2007年。ある日本の記者がフェデラーにこんな質問をしました。 「なぜ日本のテニス界からは 世界的な選手が出ないのか?」 この質問に対してフェデラーはこう答えています。 「何を言うんだ君は? 日本には国枝がいるじゃないか」 東京パラリンピックに出場する車いすテニスの国枝慎吾選手のことです。 当時からリオパラリンピックあたりまでは車いすテニス界では絶対王者とも言うべき存在で、これまでにグランドスラムでダブルスと合わせて45回の優勝という最多記録を持っています。 そんなスゴイ国枝選手ですが、長年酷使した右肘を痛め、2016年4月に手術をしたものの痛みは再発。9月のリオパラリンピックに出場しましたが準々決勝で敗退してしまいました。 その後も右肘の痛みが消えず、国枝選手は大きな決断をします。 それは、フォームの改造。肘が痛くならない打ち方への改造です。 これまで長い時間をかけて作り上げ、素晴らしい結果を残しててきたフォームを30歳を過ぎてから改造するのですから大きなリスクを伴います。 国枝選手はこう語っています。 持ってたものも一度捨てて新しい自分になろうというふうに決意してもしかしたら自分のプレーもおかしくなってしまうかもしれないっていう恐れはあったんですけどすべて変化をするという賭けに全部賭けていったというふうには思いますねどんどん進化するためにリスクを払っていこうとアベレージ(平均的)なパフォーマンスしてたらやられちゃうんで突き抜けないとダメですね 2017年は痛みを抱えながら、痛くないフォームを探しながら、そして、ツアーも続けながらのフォーム改造でした。その努力は実り、2018年の全豪、全米を制し、東京パラリンピックに出場します。