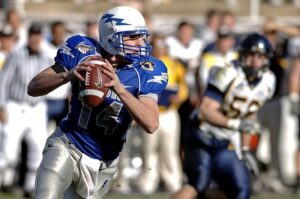2021.05.17
ピンチはチャンスじゃない。スゴい二代目
お金を払ってまで講演を聴きに行った経営者さんが掲載されたwebマガジン「Re・rise News」ナント、私にも取材が来ちゃいました。伴走舎の理念とそこに至るストーリーを語ったインタビュー動画が掲載されています。・まだ見ぬ未来から今をリライズする新時代創造マガジン「Re・rise News」・YouTubeチャンネル「Re・rise Short Story」※ 2つのどちらからでもご覧になれます。 SPA(製造小売り)の事業モデルをテコに成長したアイリスオーヤマ。コロナ禍のこの1年あまりでも、マスク、ノートパソコン、飲料水など次々に参入し、ついにはSPAのノウハウを武器に外食にまで参入しました。 この快進撃のアイリスオーヤマグループ 154,000人を率いるのが二代目の大山晃弘さん。2003年に入社して実績を積み、2018年に社長に就任。その年の売上高は4750億円でしたが、3年後の21年には8500億円と倍近くに成長させています。 アイリスで有名なのが月曜会議。社長の前で新製品についてプレゼンし、その場で決定していきます。50億円を超える投資となるマスクの国内製造への参入も、即決でした。 一兆円をめざして走り続ける大山晃弘社長はこう語ります。 変化が激しいときはやはり決断が早い会社が生き残っていくのではないかと。なかなか事前には予測できませんので、その分なにか発生したときにいかに早く対応するか、これがキーだと。 アイリスオーヤマはもともとは大阪にあった下請け仕事をこなすプラスチック工場(創業1958年)。現在は会長の大山健太郎さんが、下請けから脱するために作った漁業用のブイが第一号の製品です。 大山健太郎さんが、社長で息子でもある晃弘さんについてこう語っています。 私が50年かけてやった売上を3年で倍にするんですから何も言うことはないでしょう。 さらにつづけて大山健太郎さんが語ったことが、アイリスオーヤマのDNAなんだと思います。 ウチでは「ピンチはチャンス」じゃないんです。「ピンチ が チャンス」って言ってるんです。 ピンチ = チャンスだなんてすごい発想ですね。ピンチをチャンスとして貪欲に捉えていく、この姿勢がアイリスオーヤマの快進撃を支えているんでしょうね。 冒頭でもご紹介した、伴走舎の理念とそこに至るストーリーを語ったインタビュー動画。ぜひ、ご覧ください。・まだ見ぬ未来から今をリライズする新時代創造マガジン「Re・rise News」・YouTubeチャンネル「Re・rise Short Story」※ 2つのどちらからでもご覧になれます。