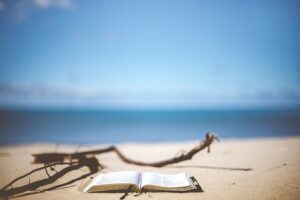2021.05.05
どちらの機会損失のほうが大きいのか?
ゴールデンウィークの沖縄、前半は晴天が多く、5月2日、3日は鯉のぼりも気持ちよさそうでしたね。昨日4日になると風が強くて、家族揃って泳ぐのも大変そうでした。さて、本番の今日の天気は... ゴールデンウィーク中、通りかかったお店の窓にでっかく営業時間が書かれていました。 営業時間や定休日は、覚えてもらいやすいのが一番です。 やってると思って行ってみてたら休みだったという経験、みなさんもありますよね。後日、再びその店へ行こうかと思ったとき「ひょっとしたらまた休みかも?」って頭をよぎりませんでしたか? みんなでお昼に出かける際、定休日がわかりにくくて「わざわざあそこまで行って、ま〜た休みだったらやだよね」ということで行かなくなった中華屋さん。いつの間にか閉店していたというお話をこのメルマガでもご紹介しましたよね。 人間は、優先順位がほとんど同じ複数の選択肢があるとき、疑問が残る選択肢は排除する傾向にあります。写真の例はお土産などによく利用される有名なお菓子屋さんなのですが、「あの店、閉店時間何時だっけ?もう閉まってるかもしれないな」と思われた時点で選択肢から外される可能性が高くなります。どうしてもその店のお菓子を手土産に持っていきたいのなら、ネットで調べて営業時間を確認するかもしれませんが。 このお店、10年ほど前に田舎に新設された大きな工場の敷地内にある店舗です。この工場から出荷される県内全域のお土産品店や直営店での販売など会社全体の売上に占めるこのお店の割合はいかほどでしょう。お店の都合もあってこのような営業時間になってるのでしょうが、せめて 月〜金 8:30〜15:00 土日祝 8:30〜17:00 水曜定休のようにもう少し覚えやすくしてもいいのではないでしょうか。 平日木曜日15:00〜17:00の2時間店を閉める機会損失と「もう閉まってるかも」とお客の頭の中から消される機会損失のどちらが大きいか。