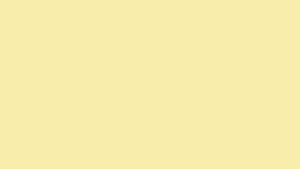2026.01.05
笑顔は、最強の経営資源
前向きさの順番について 経済環境が厳しかったり、変化のスピードが速かったりすると、どうしても先のことを考えて気持ちが重くなることがあります。状況が落ち着いてから動こう、良くなってから前向きになろう、そう考えてしまうのも自然なことかもしれません。 そんなとき、私がよく思い出す言葉があります。 「楽しいから笑うのではない、笑うから楽しくなるのだ」 ──ウィリアム・ジェームス(諸説あり) この言葉は、気分や環境が整うのを待つのではなく、まず自分のあり方を変えてみる、という視点を与えてくれます。 目次 言葉を言い換えて考えてみる前向きさの「順番」を逆にする気持ちが変わると起きること笑顔という経営資源 言葉を言い換えて考えてみる 先ほどの言葉を、少し言い換えると、こんな表現もできるのではないでしょうか。 「運がいいから楽しいのではない。楽しいから、運がやってくる」 業績がいいから前向きになる、環境が整っているから笑える。もちろん、それも一理あります。 ただ、それがいつも成り立つとは限りません。条件が整うのを待っているうちに、気持ちだけが疲れてしまうこともあります。 前向きさの「順番」を逆にする そこで、順番を逆にしてみたらどうでしょうか。不安定な状況だからこそ、まずは笑って仕事をしてみる。すると、不思議と気持ちが少し軽くなり、考え方に余裕が生まれます。 その結果、アイデアが浮かんできたり、人との関係が少し良くなったりすることがあります。気がつくと、「あれ?なんだか流れがいいぞ」と感じるような出来事が起き始めることもあります。 気持ちが変わると起きること 前向きな気持ちは、特別な出来事が起きてから生まれるものだと思われがちですが、必ずしもそうではありません。先に自分の姿勢を変えることで、見える景色や受け取るものが変わってくることがあります。 私は、こうした変化が現場で起きる場面を、これまで何度も見てきました。大きなきっかけがなくても、ちょっとした心の持ち方の違いが、その後の流れを変えることがあります。 笑顔という経営資源 笑顔は、コストゼロでできる最強の経営資源です。特別な準備も投資も必要ありませんが、職場の雰囲気や自分自身の状態に、確かな影響を与えます。 状況が簡単ではないときほど、しかめっ面で耐えるより、笑いながら工夫するほうが、次の一手が見えてくることもあります。今日一日、意識して口角を少し上げてみる。それが、流れを変える最初の一歩になるかもしれません。 公開・更新履歴2026年01月05日:公開