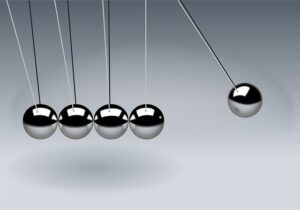2021.05.31
事業再構築。替えるか、合わせるか。
あなたは「私は正しく経営判断している」と迷わず言えますか?って聞かれると、正直、不安じゃないですか? これまで自分なりに考え判断してきたと思います。また、自分の勘を信じ、人一倍の行動力を発揮してきたと思います。 あなたの「勘」や「行動力」はもちろん経営判断にとって大切な要素です。でも、「これだ」と裏付けるものがあれば、自信を持って判断できますよね! コロナ禍で厳しい経営状況の中では、あなたの「経営判断」次第で大きく状況が変わります。 だからこそ、今回、「正しく経営判断ができる3つのスキル!セミナー」を開催します。お問い合わせを何件もいただき、開催日を追加しました。正しく経営判断ができる3つのスキル!セミナー 総予算約1.4兆円の超大型補助金、事業再構築補助金を先日このメルマガでも取り上げました。事業再構築補助金を攻める前に 政府の政策を推し進めるために用意されるのが国からの補助金です。新型コロナの感染拡大により、事業を取り巻く環境が大きく変わってしまいました。この変化は今後も続くでしょう。これまで通り事業を続けていくのは難しくなっているので、政府として中小企業の事業転換の後押しをしたい、というのがこの補助金の主旨だろうと思います。 事業転換といった場合に検討したい事例が、飲食業界のワタミとくら寿司です。 ワタミは、既存の居酒屋店舗を焼肉店へ転換していることをご紹介しました。来店の目的は?焼肉店ともう一つ、鶏の唐揚げ専門店を柱として既存店の転換を進めているようです。 一方のくら寿司は、入店してから会計してお店を出るまで店員さんと一切接触しないお店への転換を進めています。あと、テイクアウトにも力を入れており、スマホで注文・決済して、商品の受け取りは専用ボックスからお客が自分で取り出すようにして、こちらも店員さんとの接触がありません。 こうしたサービスがお客さんの安心感を呼び、売上をコロナ前に回復させ増収を続けているそうです。しかも、こうした非接触型の店舗は人件費が削減できるので、収益面でも効果が。 ワタミは言ってみれば、「商売を替える」というやり方です。それに対してくら寿司は、「商売のやり方を事業環境に合わせて改善する」というやり方でしょうか。 どちらが正解というわけではありませんし、これだけというわけでもありません。しかしながら、この2つのパターンが多いとは感じています。 一点、気をつけたいのは、ワタミ型の場合。成功事例があったり、好調な商売があるとそちらへ鞍替えしたくなりますよね。ワタミでいうと、からあげと焼き肉。どちらも好調なのですが、それだけに参入も多くレッドオーシャンといえるかもしれません。ワタミのように大手だから採用できる戦略なのかもしれません。 インタビュー動画、見ましたか? https://www.youtube.com/watch?v=ejn7a9CuJkE