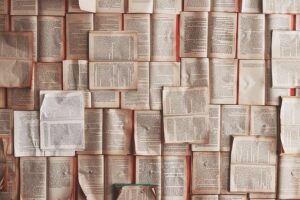2020.12.25
一歩ではなく、半歩
前回の「99敗1勝」を書いていて思い出したのが、ここで何度かご紹介している赤毛のお兄さん、カリスマ美容師の高木琢也さん。 コロナ禍で雇用情勢が厳しい中、就活を続けるひとりの男子学生が高木さんのところへ髪を切りに来ました。企業から何度も断られて自信をなくしているその学生は、目が隠れるぐらいまで前髪を長くしていました。 「顔を上げろ、前を見ろ」そんな気持ちで高木さんは彼の前髪をバッサリと切ります。 一歩でなくて、半歩でいい。自分の可能性を広げる半歩。半歩だったらギリギリのところでジャッジできるから。その代わりに、2,3個半歩出せって。そうすると見えなかったものが見えてくる。 99敗は、大きな一歩でなくてもいいです。半歩なら、失敗の影響も少なくてすみます。 あなたも私と一緒に、その半歩を99回出しませんか。