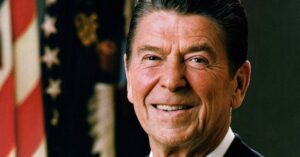2019.12.06
値引きで始まる消耗戦
先日の「値引きで失った儲けは値引率の倍以上の売上増でしか取り返せない」には、東京でサービス業の会社を経営されている社長さんから「こうやって数値に落とすとその怖さがわかります」という感想をいただきました。 売値から変動費(仕入れや材料費などの原価)を差し引いた儲けが粗利です。この粗利で固定費(人件費、諸経費)を回収します。つまり、値引きをすると粗利が少なくなるので、その分たくさん売って粗利を稼がなければならないため、固定費を回収するのが大変になってしまいます。その大変さが数値なると怖いですね。 でも、中小・小規模企業にとって取引先からの値下げ要求はつきもの。競合との競争もあれば、輸入品との価格競争にさらされている会社さんもあるでしょう。売値を下げざるを得ないなら、変動費を下げて粗利を確保するか、固定費を下げて少ない粗利でも回収しやすくするか、のどちらかです。 少しでも商品や原材料を安く買えるところを探して変動費を減らす。経費を節約したり、忙しくてもバイトを減らしたりして固定費を削減する。 もうこれは消耗戦です。 となると一番いいのは、価格を下げなくても売れる製品・サービスを持つことになりますが、簡単ではないですよね。