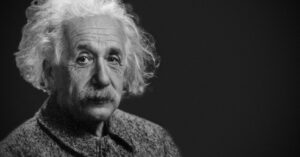2019.04.12
経営計画は仮説で立てる |「売上=客数×客単価」の「客単価」を分解する
売上は「売上=客数×客単価」と分解できます。前編では「客数」を仮説として捉え、行動につながる目標の立て方を整理しました。本記事ではもう一つの要素である「客単価」に焦点を当て、値上げに頼らず、仮説で客単価を組み立てる考え方を解説します。 目次 売上=客数×客単価、そのもう一つの要素をどう考えるか客単価は「値上げ」だけで決まるものではない価格の見せ方を工夫するという仮説商品の組み合わせを工夫するという仮説客単価もまた、仮説で組み立てるもの仮説があると、数字は「先生」になる目標とは、数字ではなく考え方を決めること 売上=客数×客単価、そのもう一つの要素をどう考えるか 売上は「売上=客数×客単価」というシンプルな式で表すことができます。前編では、このうちの「客数」を分解し、仮説にもとづいて目標を立てる考え方を整理しました。今回はもう一つの要素である「客単価」について考えてみたいと思います。 客単価という言葉を聞くと、まず「値上げ」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ただ、いきなり値上げの話になると、経営者自身も身構えてしまいますし、社員さんからも「それは難しいです」という反応が返ってきがちです。ですが、客単価は必ずしも値上げによってしか上げられないものではありません。 客単価は「値上げ」だけで決まるものではない 目標とする客単価をどうやって実現するか。考え方はとてもシンプルで、大きく分けるとやり方は二つあります。一つは「価格の見せ方を工夫すること」。もう一つは「商品の組み合わせを工夫すること」です。まずは、この基本だけを押さえておくことが大切だと考えています。 ここで重要なのは、どちらも「値段そのものを上げる」話ではないという点です。客単価は、事前の設計によって、無理なく組み立てることができます。 価格の見せ方を工夫するという仮説 一つ目は、価格の見せ方を工夫することです。これは値上げとは別の話です。たとえば、本当に買ってほしい価格帯の商品と、必ずしも買われなくてもいいけれど、比較のために置いてある商品を並べておく、という考え方があります。 人は価格を単独で判断しているようで、実際には「比較」で判断しています。「こちらのほうが、なんだかお得だな」と感じてもらえれば、自然と選ばれる商品が決まってきます。飲食店のメニュー表などでは、よく使われている考え方ですよね。 ここで立てるべき仮説は、「この価格帯の商品を基準に見せれば、こちらが選ばれやすくなるのではないか」というものです。客単価は偶然決まるのではなく、どう見せるかという仮説にもとづいて設計されていきます。 商品の組み合わせを工夫するという仮説 二つ目は、商品の組み合わせを工夫することです。こちらは、購入点数を増やすという発想です。いわゆる「買い合わせ」や「オプション」と呼ばれるものですね。 たとえば、スーパーの精肉売り場で、すき焼き用のお肉の横に、すき焼きのタレや野菜が一緒に並んでいるのを見たことがあると思います。「せっかくだから、これも一緒に」という気持ちが自然に生まれれば、結果として客単価は上がります。 この場合の仮説は、「この商品とこの商品を組み合わせて見せれば、一緒に買ってもらえるのではないか」というものです。ここでも、客単価は自然発生的に決まるのではなく、事前に組み立てられています。 客単価もまた、仮説で組み立てるもの こうして見てみると、客単価の中身は、「どんな価格をどう見せるか」「どんな組み合わせを用意するか」という設計の積み重ねでできていることが分かります。これは、前編で扱った「客数」とまったく同じ構造です。 客数も、客単価も、どちらも自然に決まるものではありません。どこをどう動かすつもりなのか。その意図が仮説として言葉になっているかどうかが、目標として機能するかどうかの分かれ目になります。 仮説があると、数字は「先生」になる 仮説をもって立てた目標は、達成しても未達でも、必ず次の一手を残してくれます。結果の数字だけを追いかけていると、期末の振り返りは「よかった」「ダメだった」で終わってしまいがちです。 一方で、仮説があれば、数字は原因を教えてくれる存在になります。どこが想定どおりで、どこがズレていたのか。そのズレは、次に何を変えるべきかを示してくれます。数字は評価の道具であると同時に、学びのための先生でもあるのだと思います。 目標とは、数字ではなく考え方を決めること 客数であれ、客単価であれ、大切なのは「どこをどう動かすつもりだったのか」が言葉になっていることです。目標とは、単に数字を決めることではなく、考え方を決めることなのかもしれません。 あなたの会社の目標は、数字を追いかけるためのゴールでしょうか。それとも、行動を導き、振り返りで学びが残る仮説としての目標でしょうか。前編と後編を通じて、そんな問いを一度立ち止まって考えていただけたらと思います。 公開・更新履歴2019年:公開2025年12月21日:大幅に加筆・再構成